【保存版】受動的な人と能動的な人の違いを徹底解説|特徴・メリットデメリット・改善・リーダー育成
1. 受動的と能動的の違いとは?
「受動的」「能動的」という言葉は、仕事や学校、日常会話でもよく耳にしますが、実は正確に説明できる人は少ないかもしれません。
- 受動的:周りの状況や指示に合わせて行動するタイプ
- 能動的:自分で考えて行動を起こすタイプ
どちらが良い悪いではなく、行動スタンスの違いです。
この記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリット、改善方法やリーダー育成のヒントまでわかりやすく解説します。
2. 受動的な人の特徴と強み
受動的な人は「空気を読んで合わせられる」タイプ。チームの安定装置として活躍します。
- 指示があればしっかり動く
- 周りとの衝突を避ける
- 協調性が高く、場の雰囲気を乱さない
- リスクを避け、慎重な行動をとる
メリット
- チームがギスギスしにくい
- 安定感がある
- 慎重なのでトラブルが少ない
デメリット
- 主体性が弱く見られることがある
- チャンスを逃しやすい
- 急な変化に対応しづらい
3. 能動的な人の特徴と強み
能動的な人は「動かす側」。課題を見つけて、周囲を巻き込みながら物事を進めます。
- 自分から提案・改善案を出す
- 責任を持って行動できる
- 新しいことに挑戦する意欲が強い
- 時には意見がぶつかることもある
メリット
- 推進力があり、物事が早く進む
- 改善や変化を起こせる
- リーダー・マネージャー向き
デメリット
- 暴走すると独りよがりになりやすい
- 他人の意見を聞きにくい
- エネルギーを使いすぎて燃え尽きることも
4. 職場での具体例
- 会議で新しいプロジェクトが始まるとき
受動的な人 → 上司の指示を待ってから動く
能動的な人 → 「私が担当やります!」と立候補する - チームでトラブルが起きたとき
受動的な人 → 指示が来るまで様子を見る
能動的な人 → 解決策を提案してすぐ動く
5. 受動的・能動的それぞれに向いている仕事
| タイプ | 向いている仕事の例 |
|---|---|
| 受動的 | サポート業務、品質管理、データ入力、経理 |
| 能動的 | 営業、新規事業、企画、リーダー職 |
6. 改善・成長のポイント
受動的な人が一歩踏み出すために
- 小さな決断(ランチを決めるなど)から始める
- 毎日1つだけ自分の意見を口にしてみる
- 「失敗してもOK」と思える場で練習する
能動的な人がバランスを取るために
- 意見を言う前に一度深呼吸
- 他人の考えを先に聞いてから発言する
- ペース配分を意識して休む
7. リーダー育成におけるヒント
受動的な人をリーダーに育てるのは簡単ではありません。
しかし、組織として「次の世代のリーダー」を作るには欠かせないプロセスです。
- 最初は明確なゴールを設定し、達成したら褒める
- やり方は任せ、過程で学ばせる
- 小さな成功体験を積み重ねて自信をつけさせる
- 失敗しても安全な環境を用意する
このプロセスを繰り返すことで、徐々に能動性が高まり、
「次も挑戦します」と自分から言えるようになります。
8. 経験談:受動的な人をリーダーに育てる難しさ
僕自身、チームの責任者をやっているときに一番苦労したのが、受動的な人をリーダーに育てることでした。
メンバーに「次の案件、この人に任せてみよう」と思ってお願いすると…
- 指示が細かすぎると、ただの作業として終わってしまう
- 指示が少なすぎると、動けずに固まってしまう
実際にやって効果があった方法
- 最初は明確なゴールを設定
「このタスクを〇日までに終わらせて、こういう形で報告してね」と伝える - 過程は本人に任せる
やり方を細かく教えず、「困ったら聞いて」とだけ伝える - 小さな成功体験を作る
できたらすぐ褒める、みんなの前で感謝を伝える
これを繰り返していくと、少しずつ能動的に動けるようになり、
「じゃあ次の案件もやってみます」と自分から言ってくれるようになりました。
9. まとめ:どちらも必要な存在
受動的・能動的はどちらも組織に欠かせません。
大切なのは、自分がどちら寄りかを知り、状況に応じて行動を変えること。
- 受動的な人 → 小さな挑戦から始めて主体性を育てる
- 能動的な人 → 周囲の声を取り入れて協調性を高める
バランスが取れたとき、チームも自分自身も一番伸びます。
あなたやあなたの部下はどちらでしょう自分の思考や部下への教え方
うまくいかない時はまた一度考えてみると良いのかもしれません。
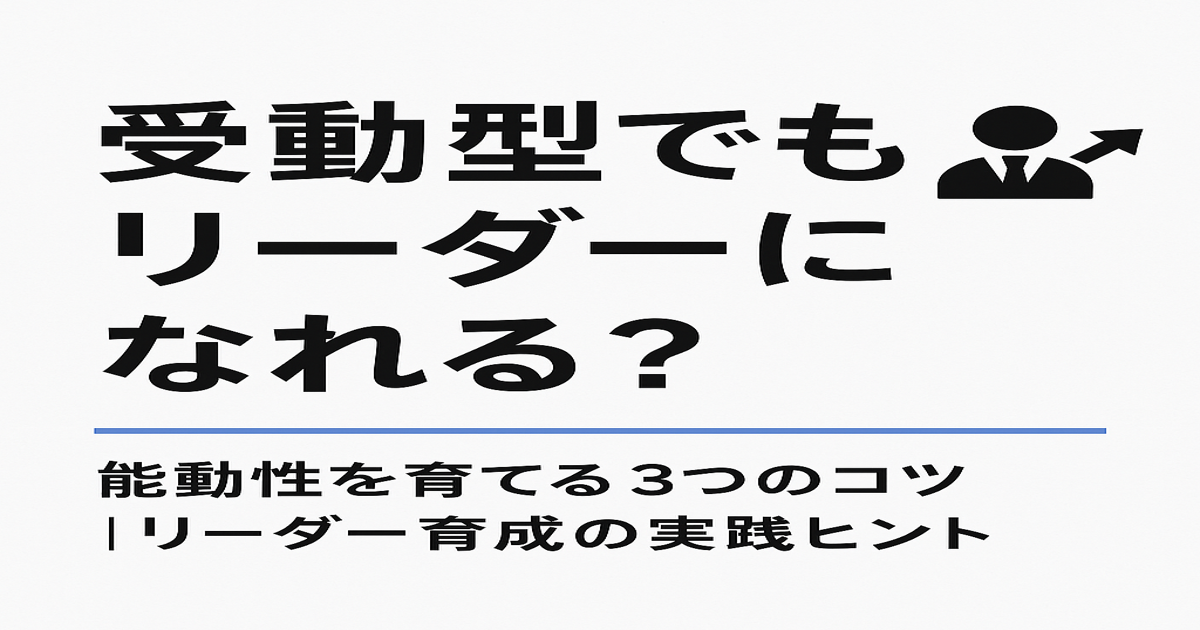
コメント